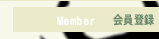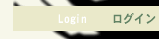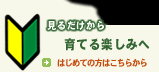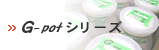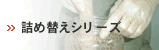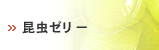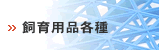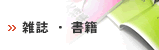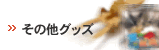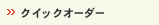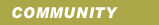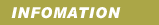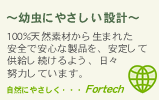菌糸ビン・・・あまり聞き慣れない言葉ですよね。これはクワガタムシの幼虫飼育では現在主流になっているもので、クワカブ愛好家の皆さまなら100%ご存じでしょう。なにやらマニアックな匂いがぷんぷんとしてきましたね。 |
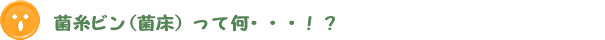
菌糸ビンとは、粉砕した広葉樹にキノコ菌を植えて木の成分のひとつである「リグニン」を分解させ、幼虫が食べやすい「えさ」にしたものです。 菌糸ビン(菌床とも言う)は、もともとキノコを栽培するために作られたもので、広葉樹のオガ粉を腐朽させたものならクワガタ幼虫にも良いのでは・・?と考えたブリーダーさんが幼虫を入れてみたのが始まりのようです。 クワガタ幼虫飼育の主流を担う菌糸ビン。しかし、もちろん菌糸ビン飼育に適さない種類のクワガタムシもいます。カブトムシ幼虫にも菌糸ビン飼育は適しません。 今も昔もクワガタムシ飼育の王道は日本産オオクワガタ!今でも人気No.1!! |

菌糸ビンには皆さんが普段からよく食べている「キノコ」の菌が使われています。 菌というとなんとなく怖いイメージがありますよね。菌でまず思い浮かぶのが食中毒の原因となる大腸菌やピロリ菌などでしょうか。しかしこれらは細菌であって、菌糸ビンに使っているキノコ菌とは細胞構造が全く異なるものです。「キノコ」は菌類でカビに近い仲間です。本体は「菌糸」の状態で、ある条件が揃うと「キノコ」を出します。「キノコ」は胞子をつくるための器官なのです。 「菌糸ビン」作りは、「キノコ作り」と基本的にほとんど同じです。 ※G-potシリーズは専用工場で製造しています。キノコ作りに似ているのですが、G-potはクワガタ幼虫 |
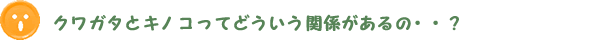
|
一見、何の関係もなさそうな組み合わせですが、クワガタ幼虫飼育にはキノコ(キノコ菌)は欠かせない存在なのです。それは何故でしょう・・? 実はクワガタ幼虫の食性とキノコ菌は深い関係にあるのです。 ほとんどのクワガタ幼虫は、広葉樹の「朽ち木」を食べて育ちます。元気のある広葉樹の中に幼虫がいることはありません。なぜ朽ち木にしか幼虫がいないのかというと、原因は木の成分のひとつである「リグニン」。これがあるとクワガタ幼虫たちは食べても消化できません。そしてこの「リグニン」を分解できる生物はキノコ菌だけなのです。 キノコ菌は広葉樹を朽ちさせる(これを腐朽と言います)役割を果たしているのです。 |

クワガタ幼虫飼育は、材飼育からマット飼育、そして菌糸ビン飼育へとブリーダーさん達の飼育に対する情熱のもと、進化し続けてきました。現在ではさまざまなオガ粉や菌種の違う菌糸ビンが発売されています。と言っても、材飼育やマット飼育がなくなったわけではなく、虫の種類や状況に応じてうまく共存しています。 私たちはクワガタ幼虫が自然の中で育つのと同じ環境を、できるだけ再現していきたいと考えています。いつまでもキノコ栽培用のビンを使わなくても、もっと幼虫に最適な形があるのではないか?と考え「スタウトボトル」を考案し(G-potスタウト1200cc)、色んな種類の幼虫に対応できるようカワラタケ菌を使った菌糸ビン(G-potカワラ)の開発などに取り組んできました。 これからも幼虫にやさしい、安全で安定した商品をお届けできるよう、いっそう努力してまいります。 |
 |
→G-potシリーズご注文&詳細ページへ |